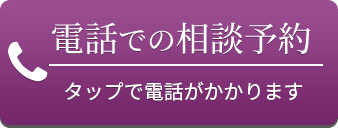小堀球美子の相続コラム
遺留分減殺請求権がないことの確認を求める訴え
通常、裁判は、いくらを支払えなどという給付の訴えで解決できる場合には、いくらの請求権があることの確認を求めても、それは通常は解決には迂遠であるので、不適法として却下されます。
同じく過去の法律関係事実関係の確認を求めても現時点の解決にはならないので、これも不適法として却下されます。
たとえば、被相続人が法定相続人Aに全ての遺産を遺すという遺言を書いて、死亡したとき、他の法定相続人Bは遺留分減殺請求権を行使しました。ところが、この遺留分減殺請求権の行使は、裁判外でもでき、また、遺留分減殺請求に対しては、被請求者は価額弁償の意思表示ができ、その場合、AB間で、AがBに価額弁償する金額の交渉になります。
しかし、この交渉は通常「遺留分算定の基礎となる遺産の範囲、遺留分権利者に帰属した持分割合及びその価格を確定するためには、裁判等の手続において厳格な検討を加えなくてはならない」(後述最高裁判決)ので、Aが弁償金を払いたくても、Bが応じないとき、Aとしては、解決の道が途絶えてしまいます。
そこで、AがBに対して、Bの遺留分減殺請求権は一定の金額を超えては存在しないことの確認を求める訴えを起こしました。この訴えは適法か。
Bが価格弁償請求権を行使する旨の意思表示をしていない現段階では、価格弁償請求権が確定的に発生しているといえず、現在の法律関係の確認を求めていないので、不適法か、という問題が最高裁まで争われました。
最高裁第3小法廷は、平成21年12月18日判決で、上記の理由で確認の利益を欠き不適法と判断した原判決を破棄し、原審へ差し戻しました。
最高裁は「弁償すべき額について当事者間に争いがあり、受遺者等が判決によってこれが確定されたときには速やかに支払う意思がある旨を表明して、弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは、受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り、上記訴えには確認の利益があるというべきである」としました。
遺留分減殺請求されて、価額弁償の意思も表明したのに、何も請求してくれない遺留分権利者に対する受遺者(「相続させる」とされた人)にとっては、手をこまねいて待っているだけではないということですね。
2011-03-24|タグ: